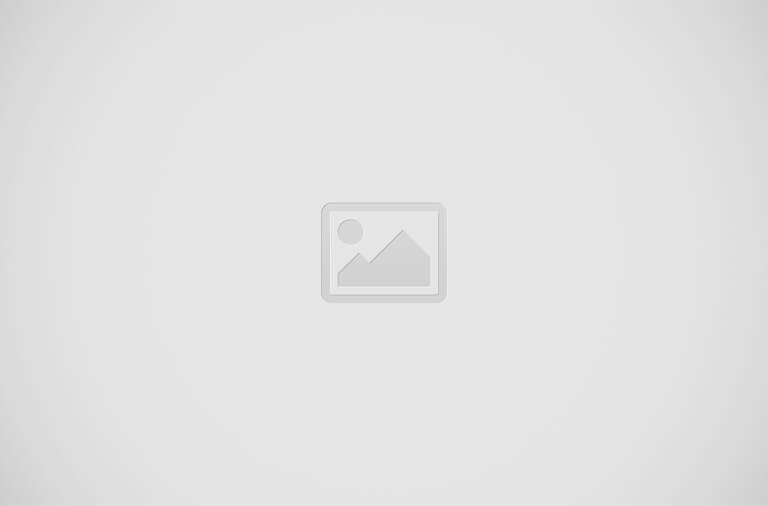たかられてると気づき軽く空しさを覚えた僕だったが、
実はこのカタベイで、チャレンジしようと思っていた事がある。
カービング(彫刻)を習いたい。
元々お面が好きで、以前から外国に行っては
キモいお面を買って家に飾ってはいたのだが、
最近にわかにその熱が上がっていたのだ。
というのも、アフリカに来て以来、
お面に限らず人の手によってつくられた
素敵なグッズに出会う事が多く
とても刺激を受けていたのだ。
またその多くが、(美和も書いていたが)
不要品として一度命を失った素材からの
リサイクル品だった。
僕はこの「手作り」「リサイクル」を
アフリカンスピリットと受け止め、
アフリカ旅行中にどこかで師匠を見つけて
弟子入りしようと考えていた。

リビングストンで最高にカッコいいアフリカンカフェがあった

そこでステージに並んでいた演奏者たちはワイヤー(針金)製

ケープタウンで見かけたレコードリサイクル品
カタベイについた僕は早速お師さん探しに勤めた。
政府が指定したというクラフト街に行っては
そこで作業している人を探して話しかけ、
バーに行っては出会うローカルに相談する。
が、誰と話しても「俺がNo.1」だ「あれは俺がやった」
となりどうも信用ならない。
価格も全て交渉なので全然バラバラ。
「1日3時間×2日でお面を一緒につくる」
と設定しレッスン料から材料費まで込み込みで話すと
とにかく仕事を取ろうと2,000クワチャ(1,200円)まで下げる奴から、
強気の交渉で1時間2,000クワチャ(→トータル6時間で12,000クワチャ!
と来る奴まで。
そんな中、町のはずれの小さな小屋で
黙々と作業する1人の男性に出会った。

仕事ぶりを見せてもらいつつ話を始めると
なんとも柔らかい雰囲気で売り込みモードもゼロ。
そして何より仕事が早い。
かわいらしい動物チェスセットを黙々と作り続ける。

木の破片はものの20分でかわいい動物に変わるが、
その後サンディング(磨き)、ポリッシュ(色をつけて磨く)、
プラスティックの破片を削った牙や爪をつける作業、
細かくて丁寧な仕事っぷりだった。


アユーブ・ンベヤ52歳。
思い描いていた「お師さん」のイメージそのものの彼に、
僕は師事することを決めた。
(価格もお面作り2-3日込み込み2000クワチャにしてくれた)
カタベイ滞在3日目からレッスンは始まった。
その日はラマダン最終日でイスラム教徒の彼にとって
翌日は休日、さらにその翌日から数日間は実家に帰る、
ということで初日の後4日ほど肩すかしを食らったのだが、
とにかく待望のお面づくりの日々が始まった。

木の破片から始まり(この大きさにのこぎりで切るだけで相当大変だった・・・)

少しずつ少しずつ形をつくっていく

時に小さな破片などを使いレッスンを受けつつ

実際にトライするが力の入れ具合、角度、なかなかうまくいかない

目をつくる作業はひとつ間違うと簡単に壊れてしまう本当に細かい作業だった

口数は多くないが優しく包んでくれる、まさに「お師さん」だった。


*
一方その間・・・
ただ待っているだけではつまらない、
と美和も師匠を探していた。
まず探したのは裁縫の先生だった。
簡単な移動時などに使える口の大きなバッグを、
マラウィの布で作って欲しいと僕がお願いしたのだ。

マーケットの一角の小さな作業場で

本当に丁寧に教えてくれた

長いブランクとこのマニュアルミシンに最初手こずっていた

何かあると「ティーチャー!」「うまい!」とご機嫌を取る

予定の2時間より大幅に延長して4時間かかったけど無事完成
続いて彼女が選んだのは、この男性。
バンブーショップというなかなかシャレた店で
いつ見ても何かを作っている彼は、
自らをマシン(機械のように働き続けるから)と紹介した。
 ■
■
この店はワイヤーでつくったアクセサリーを置いており
町中探してもここ程のクオリティと品揃えの店は無い。
話をしても町の他の人たちとは違う洗練された雰囲気だ。
最初はイケメン候補として写真を撮っていた美和だったが、
数日後には彼を2人目の先生にお願いする事を決めていた。

イヤリングからブレスレットから本当に豊富な品揃え

店のカウンターを挟んでレッスン開始

常に丁寧に教えてくれ、たまに褒める事も忘れない、最高の先生だったよう

固いワイヤーを指で細かく曲げ、仕上げはビーズで装飾。シンプルな
作業だが相当難しいらしくなかなかマシンのようにはいかない。

なんとか初日にイヤリングを完成させてこの表情

翌日には次の課題だったアンクレットも完成させた

手ごたえを感じたのか毎日宿題を持ち帰り宿でも随分練習していた
この習い事をしてみよう企画は
なかなかグッドアイディアだった。
たかられに気づき萎えた気持ちはどこへやら、
充実した気持ちでカタベイステイは日数を数えていった。
(続く)